研究室紹介
Laboratory
研究内容
地盤工学は、構造物やインフラを安全に支えるために、地面・地盤の性質や挙動を科学的に解明し、設計や施工に応用する学問です。
橋梁や建築物、道路、堤防、港湾施設など、あらゆる土木事業において「地盤」は不可欠の要素であり、地盤工学はそれらをつなぐ“土木工学のハブ”として中心的な役割を担っています。また、地震や豪雨など自然災害の影響を受けやすい地盤の安定性を確保することは、「安全で文化的な暮らし」を実現するうえで欠かせません。
本研究室では、粒状体のミクロな力学挙動の解明から、堤防や斜面の安定解析、鋼矢板などを活用した地盤補強工法の開発に至るまで、地盤に関する幅広いスケールとテーマに取り組んでいます。X線CTなどの高精度な可視化技術を活用した模型実験や地盤の構造観察に加えて、実験結果をもとにした数値解析や力学モデルの構築・検証も積極的に行っています。
実験・観察・解析を相互に結びつけることにより、現象の本質を理解し、理論と実践をつなぐ地盤工学の新しいアプローチを目指しています。多様な地盤条件や社会的課題に対応できる技術と知見を備えた人材の育成も、本研究室の重要な使命です。







-
01粒状地盤材料の内部構造と力学応答の可視化・解析
X線CTや画像解析を駆使し、粒状地盤の内部構造や変形・破壊挙動をミクロスケールで観察します。得られた情報をもとに、マクロな地盤力学特性との関連性を明らかにし、現象の本質的理解を深めます。
-
02環境調和型防災インフラの構築に向けた地盤–植生相互作用の評価
植物の根系が地盤構造物の安定性や侵食抵抗性に与える影響を実験的に検証し、自然環境と調和する地盤防災技術の可能性を探ります。越水時の堤防ロバスト性向上など、新たなアプローチを提案しています。
-
03粒子特性に基づく地盤材料の性能設計と新素材開発
粒子の形状や表面性状が地盤材料の支持力や変形特性に及ぼす影響を模型実験により分析します。人工マテリアルや新素材を活用し、地盤構造物の性能向上につながる材料設計指針の構築を目指します。
-
04数値解析による地盤挙動の予測と設計理論の高度化
離散要素法や有限要素法を用いて、地盤–構造物系の挙動を再現・解析し、液状化対策や地盤改良の効果を評価します。実験との連携により、既存設計法の検証・高度化につながる定量的な知見を提供します。
環境
研究室
熊本大学工学部1号館
421号室(高野教員室)・406号室(学生研)

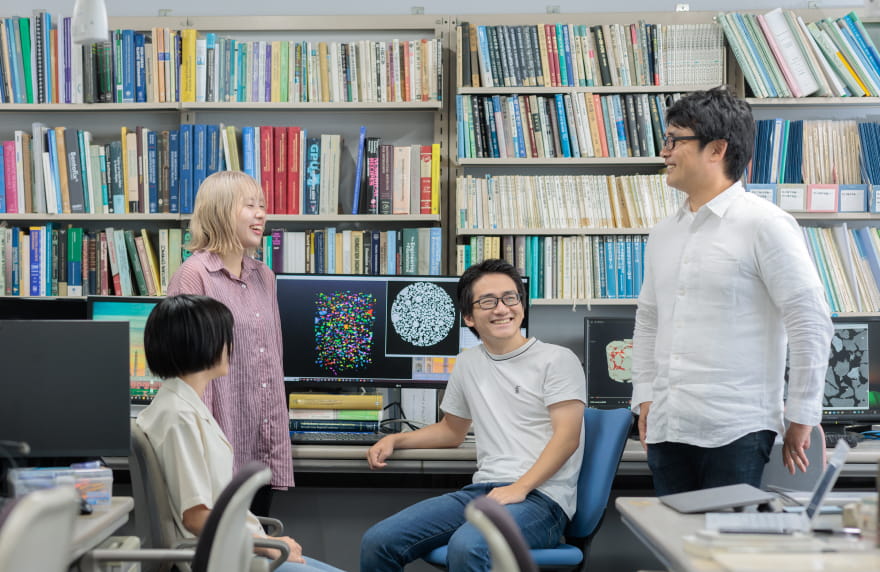
実験室


当研究室では、地盤材料や地盤構造物の挙動を多面的に解明するための充実した実験設備を備えています。三軸圧縮試験装置(静的・繰り返し載荷対応)、一面せん断試験機、各種圧密試験装置といった要素実験機器に加え、侵食挙動の再現に用いる水路模型や、杭基礎の載荷挙動を評価するための大型模型実験装置など、幅広いスケールと目的に応じた設備を整備しています。特筆すべきは、研究室内に3台のX線CT装置を保有している点です。これにより、供試体内部の粒子構造・変形・破壊の進行を非破壊かつ三次元で連続的に可視化でき、粒状体のミクロな挙動とマクロな力学応答との橋渡しを可能にしています。これらの施設群は、基礎力学の探究から応用技術の開発まで、地盤工学の幅広い研究課題に対応できる柔軟かつ高度な実験環境を提供しており、学生教育や共同研究の場としても活発に活用されています。
設備
Nikon XT H320
高出力高解像マイクロX線CTスキャナ

BRUKER SKYSCAN 2214
ナノスケール 3D X線顕微鏡

TOSCANNER 32300
マイクロフォーカスX線CTスキャナ

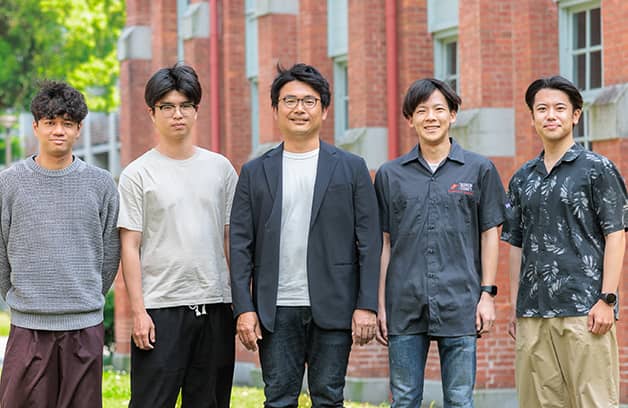
准教授・在籍メンバーについて
