6月26日(火)熊本大学百周年記念館において、第2回地域防災セミナーが社会環境工学専攻、政策創造研究教育センター、くまもと地域基盤政策研究所により共同開催されました。このセミナーは、市民の防災意識の向上と啓発を目的として毎年行われています。今年のテーマは「リスクコミュニケーション-緊急時の官民連携をどうするか」であり、非常に多くの方に参加していただきました。150名以上の参加者によって会場は満席となり、新たに臨時の席を設ける必要がでるほどでした。
セミナーでは、まず、片田敏孝氏(群馬大学教授)が、各地の地域防災の取り組みの中で、住民に接して感じたこと、その中で見つけた効果的な住民とのコミュニケーションのあり方などを紹介されました。 土屋智子氏(電力中央研究所上席研究員)は、臨界事故を契機に立ち上がった東海村のリスクコミュニケーション活動を、臨界事故時の問題点や事故後の住民意識、村の社会経済環境を加えながら紹介されました。その後、緊急時の産官学連携のあり方について、国の立場からは島元尚徳氏(熊本河川国道事務所調査第一課長)、県の立場からは奥村政治氏(熊本県熊本土木事務所工務一課長)、民の立場からは坂田信介氏(熊本県建設業協会芦北支部長)、マスメディアの立場からは中村俊隆氏(熊日社会部次長)にご講演いただきました。白川出水時の防災活動や災害発生時の支援活動協定についての説明のほか、災害緊急時の応急措置に地元建設業界のボランティアが非常に重要な役割を果たしていることについて話していただきました。
土屋智子氏(電力中央研究所上席研究員)は、臨界事故を契機に立ち上がった東海村のリスクコミュニケーション活動を、臨界事故時の問題点や事故後の住民意識、村の社会経済環境を加えながら紹介されました。その後、緊急時の産官学連携のあり方について、国の立場からは島元尚徳氏(熊本河川国道事務所調査第一課長)、県の立場からは奥村政治氏(熊本県熊本土木事務所工務一課長)、民の立場からは坂田信介氏(熊本県建設業協会芦北支部長)、マスメディアの立場からは中村俊隆氏(熊日社会部次長)にご講演いただきました。白川出水時の防災活動や災害発生時の支援活動協定についての説明のほか、災害緊急時の応急措置に地元建設業界のボランティアが非常に重要な役割を果たしていることについて話していただきました。

パネルディスカッションでは、これまでの講演内容を踏まえて、松田泰治氏(熊本大学教授)の司会のもと、パネラーの土屋智子氏、島元尚徳氏、奥村政治氏、坂田信介氏、中村俊隆氏によって活発な議論が繰り広げられました。また、会場の参加者からも多くの発言があり、議論は大変盛り上がりました。
[当日のプログラム]
13:00〜13:05 開会の挨拶
熊本大学工学部社会環境工学科長 山尾 敏孝
13:05〜14:05 「住民の心に寄り添う地域防災」
群馬大学大学院教授 片田 敏孝
14:05〜15:05 「東海村における原子力リスクコミュニケーション活動」
電力中央研究所上席研究員 土屋 智子
休憩(10分)
15:15〜15:30 「白川が氾濫した場合の市街部における円滑な避難計画を実現するための方策について」
熊本河川国道事務所調査第一課長 島元 尚徳
15:30〜15:45 「大規模災害発生時における支援活動に関する協定」
熊本県熊本土木事務所工務第一課長 奥村 政治
15:45〜16:00 「緊急時の官民連携:民の立場から」
熊本県建設業協会芦北支部長 坂田 信介
16:00〜16:15 「災害緊急時のメディアの役割」
熊日社会部次長 中村 俊隆
16:15〜16:30 「くまもと地域政策基盤研究所について」
熊本大学工学部社会環境工学科長 山尾 敏孝
休憩(10分)
16:40〜17:25 パネルディスカッション「災害緊急時の官民連携のあるべき姿」
17:25〜17:30 閉会の挨拶
熊本大学工学部教授 松田 泰治

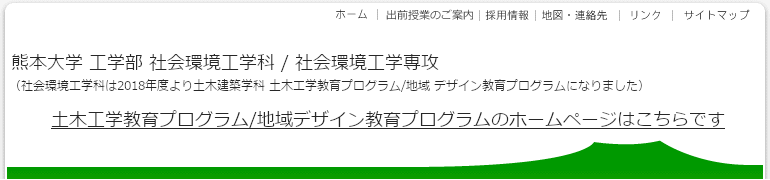

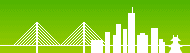
 土屋智子氏(電力中央研究所上席研究員)は、臨界事故を契機に立ち上がった東海村のリスクコミュニケーション活動を、臨界事故時の問題点や事故後の住民意識、村の社会経済環境を加えながら紹介されました。その後、緊急時の産官学連携のあり方について、国の立場からは島元尚徳氏(熊本河川国道事務所調査第一課長)、県の立場からは奥村政治氏(熊本県熊本土木事務所工務一課長)、民の立場からは坂田信介氏(熊本県建設業協会芦北支部長)、マスメディアの立場からは中村俊隆氏(熊日社会部次長)にご講演いただきました。白川出水時の防災活動や災害発生時の支援活動協定についての説明のほか、災害緊急時の応急措置に地元建設業界のボランティアが非常に重要な役割を果たしていることについて話していただきました。
土屋智子氏(電力中央研究所上席研究員)は、臨界事故を契機に立ち上がった東海村のリスクコミュニケーション活動を、臨界事故時の問題点や事故後の住民意識、村の社会経済環境を加えながら紹介されました。その後、緊急時の産官学連携のあり方について、国の立場からは島元尚徳氏(熊本河川国道事務所調査第一課長)、県の立場からは奥村政治氏(熊本県熊本土木事務所工務一課長)、民の立場からは坂田信介氏(熊本県建設業協会芦北支部長)、マスメディアの立場からは中村俊隆氏(熊日社会部次長)にご講演いただきました。白川出水時の防災活動や災害発生時の支援活動協定についての説明のほか、災害緊急時の応急措置に地元建設業界のボランティアが非常に重要な役割を果たしていることについて話していただきました。
