|
|
2007年04月 のバックナンバー「九州デザインシャレット」が熊大通信で紹介されました
『地域とともに』は大学と地域がいかに連携していくのか、という課題に対する様々なアプローチを紹介するコーナーです。複雑に要素が絡み合うまちづくりの課題を、学生主催による学生参加型のワークショップによって解決していこうという九州デザインシャレットの取り組みが、学生をサポートする指導講師、学生スタッフ、参加者の三様の立場から語られています。 九州デザインシャレットが始まった経緯、学生スタッフと指導講師陣の協力体制、準備段階での地元との関わり方、参加者と地域住民とのコミュニケーションといった裏話も載っており、最後は九州デザインシャレットを開催することで変わっていく大学と地域、そして九州全土を巻き込んだ大きな夢で締めくくっています。三人に共通しているキーワードは“知”と“つながり”・・・詳しくは熊大通信をご覧下さい。 平成18年度の土木環境系優秀者が決まりました!4月6日に行われた新年度のガイダンスで、各学年から選出された平成18年度土木環境系優秀学生一名が発表・表彰されました。 学年 氏名 理由
今後とも、あらゆる場面での学生の皆さんの御活躍を期待しています。 H18年度3年生担任:川越・大津 ようこそ,社会環境工学科へ!
社会環境工学科として2年目となる本年度は,72名の新入生を新たに迎えました。入科式では,山尾学科長の新入生への祝辞の後,教職員紹介が行なわれました。教員紹介では,名前の紹介だけにとどまらず,先生方の専門や新入生への激励の言葉が述べられ,新入生は熱心に聞き入っていました。入科式の後は,4グループに分かれて,若い先生方に誘導されながら,学内の主な施設の紹介とともにオリエンテーリングが行われました。
小林教授が座長を勤める「白川市街部景観・親水検討会」に関する記事が掲載されました
明午橋−大甲橋間(緑の区間)では、河川改修に伴い、景観設計、そして樹木の移動が計画されています。樹齢100年を含む100本超にも及ぶ樹木の移動は、「森の都・熊本」を象徴するような大事業です。今回は、樹木の移植の前に行われる“根回し”の作業が取り上げられました。 「根回し」とは・・・移植の際に樹がわるべく弱らないように行う下準備です。簡単に述べると、支持している主な根っこ以外を切断し、移植する際のますの大きさに合わせて土と根を残し、特殊なシート囲み、シートの内側で新しい根っこを発生させる工程です。その下準備により、移植しても根が十分に踏ん張れるようになります。
平成18年度太田育英奨学金を受けた学生の言葉が届きました(その2)社会環境工学科は、卒業生や旧教官の寄付によって創設された基金によって、本学科の学部及び大学院に在学中の学生に対して、独自の奨学金・表彰制度を有しています。 今回紹介する「太田育英奨学金」は、本学科昭和15年卒業生の太田豊氏の意思による奨学基金で、学業成績、人格がともに優れた学生、もしくは経済的事情で学資の支弁が困難な学生の内、学業意欲が旺盛と認められる者に奨学金を支給しています。
このたび、平成18年度太田育英奨学金を給付していただき、心より御礼申し上げます。 最近では、入社試験や昇任試験における英語能力の判断基準に、英検よりもTOEICのスコアを重要視する傾向があるようです。しかし私は今までTOEICを受験したことがなかったので、この機会に初めて受験をいたしました。その結果、私自身が最終目標とするスコアにはまだまだ届きませんでしたが、試験がどのようなものかを実際に感じ、自分の現在の英語能力レベルを知ることができました。さらに、リーディングよりもリスニングのほうが弱点であるということも痛感させられました。このことを踏まえて、今後も英語の勉強に励み、定期的にTOEICの受験をしていきたいと考えております。 書籍・雑誌に関しては、今年度は主にビジネス誌の購読を行いました。今まで聞いたことの無かった企業の話や、各分野の第一線で働く人たちのインタビューの記事を読むことで、私は今まで狭い視野で世の中を見ていたということに気付かされました。また、雑誌に紹介されていた勉強方法が、後述する資格試験の勉強の際にも役立ちました。 資格取得に関しては、今年度は宅地建物取引主任者資格試験を受験し、合格することができました。資格試験に合格できたことも嬉しく思っておりますが、その過程で勉強した内容が私にとって有益であったと考えております。実際、今回初めて民法の勉強をしたのですが、理解するのが難しい部分は多々あったものの、日常生活に密接した内容でもあり楽しく学ぶことができました。今年度も資格試験の受験を考えておりますが、試験の日程などを見て検討していこうと思います。 上述したとおり、上記の項目は今年度だけにとどまらず来年度以降も継続して行っていきたいと考えております。さらに、大学院で学ぶ中で新たな目標が見つかる可能性もあります。これからも、熊本大学工学部環境システム工学科土木環境系教室を卒業した者として、日々邁進していく所存であります。 平成18年度太田育英奨学金を受けた学生の言葉が届きました(その1)社会環境工学科は、卒業生や旧教官の寄付によって創設された基金によって、本学科の学部及び大学院に在学中の学生に対して、独自の奨学金・表彰制度を有しています。 今回紹介する「太田育英奨学金」は、本学科昭和15年卒業生の太田豊氏の意思による奨学基金で、学業成績、人格がともに優れた学生、もしくは経済的事情で学資の支弁が困難な学生の内、学業意欲が旺盛と認められる者に奨学金を支給しています。
この度、太田育英奨学金を授与していただき誠にありがとうございました。私の専門は交通計画であり、熊本電鉄のLRT(ライト・レール・トランジット)化計画案が研究対象でした。そのため、この奨学金をヨーロッパのLRTをはじめとする交通システムの視察費用に当てさせていただきました。以下、視察した都市を挙げます。 ドイツ:フランクフルト、マインツ、ダルムシュタット、マンハイム、ハイデルベルク、カールスルーエ、フライブルグ これらの都市を視察する中で、まず衝撃を受けたのが都市の賑わいでした。例えば、ドイツのフライブルグという都市は、人口約20万人で訪れたのが平日の15時頃にも関わらず、同規模の日本の都市と比較すると信じられないぐらいの人が街中を歩いていました。そして、この中心市街地に活気を産むような交通システムがうまく機能していると感じました。以下、気付いたこと・感じたことを挙げます。 ・LRTは街中でもかなりの高速走行を行っているにも関わらず騒音・振動が少なく静か。日本の路面電車とはかなり違う。運行間隔も数分で非常に便利。また、低床車両のため乗りやすい。実際、高齢者や車椅子の方を多数見かけた。 今後、日本の都市が環境問題や高齢化社会に対応するために、ヨーロッパの都市計画・交通計画から学ぶべきところは多いと思います。そして、それを実際に自分の目で見ることができたことは非常に良い経験となりました。今春よりコンサルタントに勤務することになりますが、この経験を生かして少しでも大きく社会貢献できればと考えております。最後に太田奨学金を授与していただいたことに重ねて御礼申し上げます。 各教員の研究概要をアップしました研究テーマのページに,各教員の研究概要をアップしました。 |



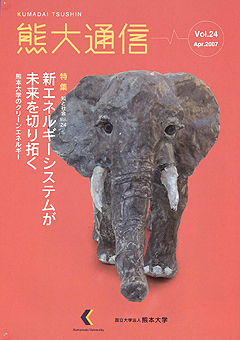 2005年から毎年開催している学生向けのデザインワークショップ(設計演習)である「九州デザインシャレット」が熊大通信vol.24の『地域とともに』(P.12〜P.13)というコーナーで紹介されました。今回の記事では、小林一郎教授、中島幸香さん(昨年度の小林研究室D1)、高木雄基くん(星野研究室B4)のコメントが掲載されています。
2005年から毎年開催している学生向けのデザインワークショップ(設計演習)である「九州デザインシャレット」が熊大通信vol.24の『地域とともに』(P.12〜P.13)というコーナーで紹介されました。今回の記事では、小林一郎教授、中島幸香さん(昨年度の小林研究室D1)、高木雄基くん(星野研究室B4)のコメントが掲載されています。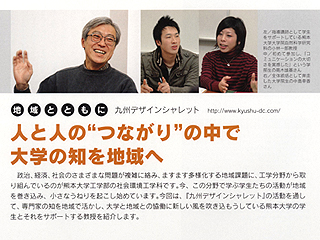



 現在、白川市街部においる景観・親水を考えるために「白川市街部景観・親水検討会」が結成されており、小林教授は座長を勤められています。今回はその会の中で整備の方向が決定され、現在整備が進められている“明午橋ー大甲橋間(通称:緑の区間)”に関する記事が、平成19年4月2日の熊本日日新聞に掲載されました。
現在、白川市街部においる景観・親水を考えるために「白川市街部景観・親水検討会」が結成されており、小林教授は座長を勤められています。今回はその会の中で整備の方向が決定され、現在整備が進められている“明午橋ー大甲橋間(通称:緑の区間)”に関する記事が、平成19年4月2日の熊本日日新聞に掲載されました。 小林教授は「白川市街部景観・親水検討会」の座長を勤められ、整備全体の方向性を検討しています。また、緑の区間における景観設計の監修を星野准教授及び星野研究室で行っています。緑の区間の整備に関する情報は、国土交通省熊本河川国道事務所HPをご覧下さい。
小林教授は「白川市街部景観・親水検討会」の座長を勤められ、整備全体の方向性を検討しています。また、緑の区間における景観設計の監修を星野准教授及び星野研究室で行っています。緑の区間の整備に関する情報は、国土交通省熊本河川国道事務所HPをご覧下さい。